大会理念

2019年10月31日、うちなーんちゅ(沖縄の方言で沖縄生まれの人を指す)が琉球文化の象徴として世界に誇ってきた首里城は、原因不明の火災により地域住民が立ち尽くす中、為す術もなく那覇の街からその姿を消しました。琉球王国創立以来、歴史上5度目の焼失です。
沖縄は、歴史を紐解けば1879年の琉球処分に至るまで、450年もの長きに渡り琉球王国として歴史を刻んできました。江戸幕府の継続が約265年であることから比較しても、それがどれだけ長い時間なのかイメージ出来るでしょう。
琉球王国の平和と繁栄を守る砦であり、歴史の象徴として語り継がれるものこそ〝首里城〟です。それは、歴史に幕を下ろし146年もの月日が経とうとも、うちなーんちゅのアイデンティティーであることに変わりはありません。かつての琉球王国では、首里城を行政の中心とし、明王朝との朝貢貿易によりアジア各国を結ぶ中継貿易で栄耀し、自らを「万国津梁」=‘世界の架け橋’と称していました。ひとたび航海に出れば諸外国からの交易品や特産品に加え、海外の文化や情報までもが伝わる、まさにアジア貿易の中心として飛躍的に発展したのです。
昨今の沖縄では、観光産業を県の主な産業とし、年間観光客数はハワイを上回り1,000万人を超えるまでになりました。しかし、新型コロナウイルス感染症の猛威により観光客数は70%程度にまで減少し、回復の兆しを見せつつも以前のようにはまだ程遠い状況です。
コロナ禍の収束を経て、観光への機運が高まる今、2026年には首里城の復興、再建が控えています。沖縄が世界に誇る首里城の再建は、住み暮らす沖縄県民はもちろん、沖縄に訪れる全ての方が心待ちにしていることでしょう。そして首里城再建は単なる観光資源の復興だけではなく、沖縄の更なる発展と、世界の架け橋となる為のひとつのシンボルとして、私たちの意識の中に確立していかなければなりません。
「第44回全国城下町シンポジウム沖縄那覇大会」は、首里城復興への機運を高めるとともに、琉球の先人達が築いてきた栄光の歴史を学び、「うちなーんちゅ」としての誇りを日本全国に、そして世界に向けて発信するための大会とします。
理事長及び実行委員長あいさつ

私たちの住み暮らす沖縄県は、歴史を紐解けば1879年の琉球処分に至るまで、450年もの長きに渡り琉球王国として歴史を刻んできました。
琉球王国の平和と繁栄を守る砦であり、歴史の象徴として語り継がれるものこそ〝首里城〟であります。かつての琉球王国では、首里城を行政の中心とし、明王朝との朝貢貿易によりアジア各国を結ぶ中継貿易で栄耀し、自らを「万国津梁」=‘世界の架け橋’と称していました。ひとたび航海に出れば諸外国からの交易品や特産品に加え、海外の文化や情報までもが伝わる、まさにアジア貿易の中心として飛躍的に発展しました。
しかし、琉球文化の象徴として世界に誇ってきた首里城は2019年に5度目の焼失があり、大きな喪失感を味わいました。2026年に首里城の復元を控えている今、首里城復興への機運を高めるとともに、琉球の先人達が築いてきた沖縄の歴史、文化、伝統を学び、「うちなーんちゅ」としての誇りを日本全国に、そして世界に知って頂くための大会とします。
一般社団法人那覇青年会議所理事長
玉城 大地
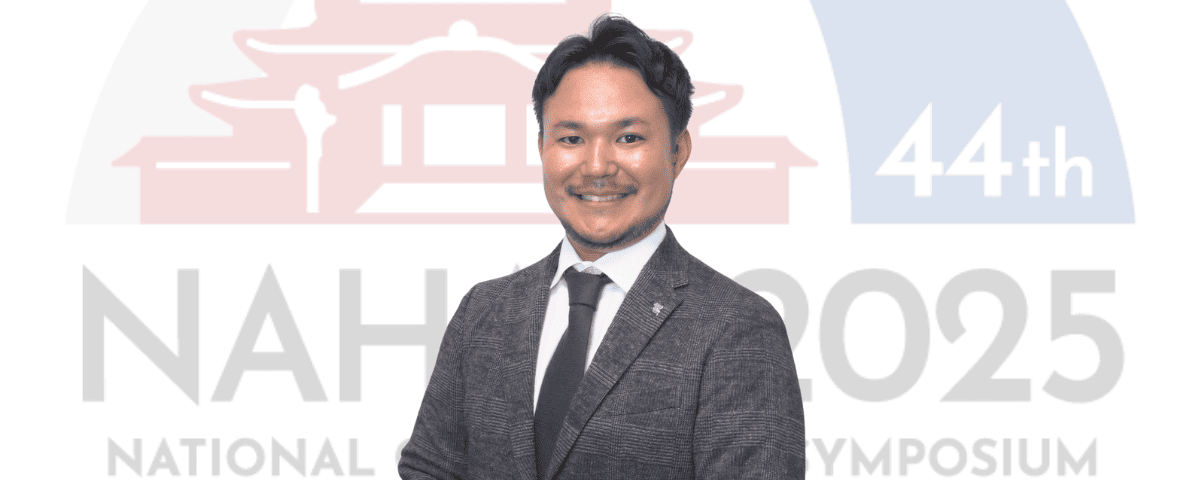
全国城下町シンポジウム実行委員長の大盛志門です。
本大会では「万国津梁~沖縄の誇りを世界に」と言うテーマを掲げ運動を展開しております。万国津梁=世界の架け橋となる為に、「地域愛を持ってグローバルな視点を持つことの大切さ」を大会のメッセージとして発信して参ります。当委員会が本大会で目指しているところは、参加される皆様がワクワクし、心から楽しみ、その中で学びや気付きに触れ合ってもらうことです。
長い沖縄の歴史を振り返れば、沖縄戦やアメリカ統治など私たち沖縄県民には忘れることが出来ない大きな出来事があります。しかし更に歴史を遡れば、琉球大交易時代とも呼ばれ中継貿易によって繁栄した歴史もございます。そして現在の私たちに受け継がれている郷土芸能や文化の数々は、そのどれもが長い時代を渡っ脈々と受け継がれてきた、正に歴史と先人達の想いの賜物であると私は考えております。
だからこそ本大会では、我々が受け継いできた「おもてなしの心」、「人々を喜ばせたいと思う気持ち」を忘れずに参加される皆様をお迎えいたします。
そして44年間の歴史が詰まった「全国城下町シンポジウム」と言う大会を大いに盛り上げ、更なる価値と存在感を持った大会にすべく、全身全霊で創り上げて参ります。多くの皆様と那覇の地でお会いできることを楽しみにしております。
全国城下町シンポジウム実行委員長
大盛 志門
